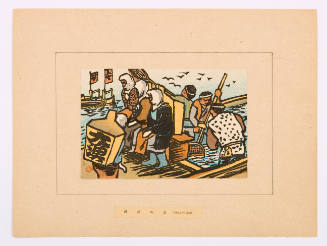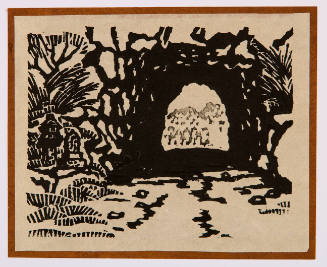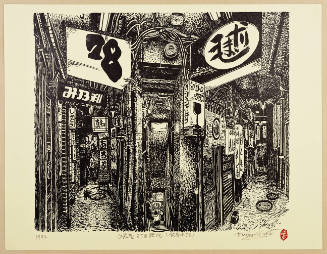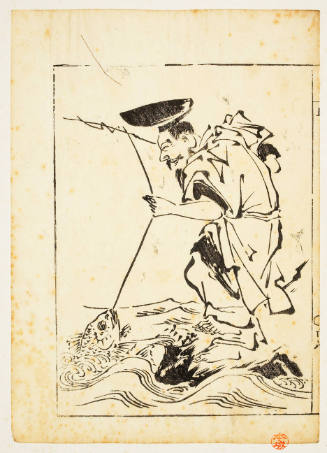Funazaki Kōjirō
Japanese, 1900 - 1988
1900(明治 33)年 6 月 11 日兵庫県尼崎市に生まれる。
旧制伊丹中学中退。はじめ日本画を志し、京都で川合玉
堂に学んだという。1918 年に上京。昭和のはじめまでに
創作版画家との交流が始まったとされるが、『詩と版画』
第 3 輯(1923.7)で告知された「船崎光次 ( ママ ) 郎作品
頒布会」の内容は絵画と彫刻である。1926 年に樺太へス
ケッチ旅行に赴き同地が気に入り、翌年(1929 年とする
資料もある)『樺太日々新聞』に入社して移住。樺太の風
景や高山植物に魅せられ、同時に木版画に道を定める。
1931 年第 1 回日本版画協会展に《葡萄》《桃》《風景》で
初入選、第 2 回展から会員となり、第 4 回展まで出品を
続ける。また、1931 年の第 9 回春陽会展にも《芍薬》《椿》
を入選させている。『樺日』記者時代は短かったと推察さ
れるが、樺太にはその後もしばしば渡り、植物に取材し
た制作も続けて牧野富太郎や武田久吉の図鑑編纂に協力
したという。牧野による解説が付されたシリーズ『華容
図聚』はこの頃(1930 年代前半)の作か。1934 年ホクト
社第 5 回展に《女待宵草》を出品し、翌年「新興美術家
協会」の結成に参加。1940 年日本版画協会が企画した『新
日本百景』に《海馬嶋烏帽子岩》で参加、またおそらく
同年『樺太名勝八景』を刊行。1942 年に千葉県夷隅郡御
宿町に移住、木版画集『房総風物聚』に着手(同年のう
ちに第一〜三輯を完成、第四輯は戦後の 1965 年に完成か。
第五〜七輯も予告されたが未確認)。戦後まもない 1947
年には武田久吉の『高山花譜』に自刻自摺の木版挿図を
数多く寄せ、代表作としている。1957 年『御宿:船崎光
治郎自刻版画誌 No.1』を日本観光美術協会より創刊(樺
太特産の植物集として第二輯が、外房をテーマとして第
三輯が予告されるが未確認)。1964 年に千葉県茂原市に移
り、木版画の講習会を開催するなかで研究会への気運が
高まり、翌年千葉市において「版画を作る会」を発足さ
せる。同会には安西七郎や金子周次も参加した。1966 年
館山市で船崎光治郎木版画作品展覧会(いとう屋)を開催。
1974 年には代表作『高山花譜』の挿図のみを再摺して(一
部は改刻・新作も追加)木版画集とし、改訂自家版第一
輯として再刊している(第二輯、三集も予告されるが未
確認)。1987(昭和 62)年 2 月 6 日千葉県茂原市で逝去。【文
献】船崎光治郎「私と樺太及山草」『樺太』8 ー 8(1936.8)
/船崎光治郎「失った故郷」『樺太』10 ー 1(1938.1)/武
田久吉 + 船崎光治郎『高山花譜』(富岳本社 1947)/『御
宿:船崎光治郎自刻版画誌 No.1』(日本観光美術協会
1957.11)/「登場 大衆に根ざした版画を追求する 船崎光
治郎さん」『朝日新聞』(1976.2.23)/『昭和期美術展覧会
出品目録 戦前編』(東京文化財研究所 2006)(西山)
Person TypeIndividual